メニュー
整形外科はこちら
脳神経内科はこちら
内科はこちら
健康診断はこちら
ワクチンはこちら
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00~ 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ●※ |
| 午後 15:00~ 18:00 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 |
初診の方とリハビリの方は、診療終了30分前までの受付となります。
【休診日】日祝、水曜午後、土曜午後 ※第2第4土曜
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00~ 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ●※ |
| 午後 15:00~ 18:00 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 |
初診の方とリハビリの方は、診療終了30分前までの受付となります。
【休診日】日祝、水曜午後、土曜午後 ※第2第4土曜
24時間365日ご相談を受け付けております!

コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療薬については、以下のような種類や状況があります。情報は2025年1月時点のものですので、最新情報が必要な場合は医療機関や公的機関の情報を確認してくだい。
レムデシビル(商品名:ベクルリー )
レムデシビル(ベクルリー)は、新型コロナウイルスの増殖を抑える抗ウイルス薬です。RNAポリメラーゼというウイルスの遺伝情報を複製する酵素を阻害し、体内でのウイルス増殖を防ぎます。点滴投与で使用され、主に入院中の中等症〜重症患者が対象です。臨床試験では、酸素投与を必要とする患者で回復までの期間を短縮する効果が示されています。ただし、軽症例では明確な有効性が確認されていません。副作用としては、肝機能障害や腎機能障害が報告されており、投与中は定期的な血液検査が必要です。日本では2020年に特例承認され、現在も重症化リスクの高い患者への標準治療の一つとして用いられています。
モルヌピラビル(商品名:ラゲブリオ )
モルヌピラビル(ラゲブリオ)は、新型コロナウイルス感染症の経口抗ウイルス薬です。ウイルスRNAの複製過程で誤り(変異)を生じさせ、ウイルスの増殖を抑える働きがあります。発症から5日以内の軽症〜中等症の患者、特に高齢者や基礎疾患のある重症化リスクの高い人に対して使用されます。臨床試験では、入院や死亡のリスクを約30%減少させたと報告されています。副作用は下痢、吐き気、頭痛など軽度なものが多く、他の薬との相互作用も少ないため、使いやすい薬とされています。ただし、妊婦や妊娠の可能性がある人への使用は推奨されていません。日本では2021年に特例承認され、外来患者向けの主要な治療薬のひとつとして広く使用されています。
パクスロビド(商品名:パキロビット)
パクスロビド(パキロビット)は、新型コロナウイルス感染症の経口抗ウイルス薬です。ウイルスが増殖する際に必要な酵素(3CLプロテアーゼ)を阻害し、体内でのウイルス複製を防ぎます。発症から5日以内の軽症〜中等症の患者で、重症化リスクの高い人に使用されます。臨床試験では、入院や死亡のリスクを約88%減少させる高い効果が確認されています。一方で、併用薬との相互作用が非常に多く、特に心臓病や高血圧、脂質異常症の薬などと同時使用できない場合があります。主な副作用は味覚異常、下痢、血圧上昇などです。日本では2022年に特例承認され、現在も重症化予防を目的とした第一選択薬のひとつとして使用されています。
エンシトレルビル(商品名:ゾコーバ)
ゾコーバ(一般名:エンシトレルビル・フマル酸塩)は、塩野義製薬が開発した日本発の経口抗ウイルス薬で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の軽症〜中等症の患者に使用されます。ウイルスの増殖に必要な酵素「3CLプロテアーゼ」を阻害し、体内でのウイルス複製を防ぐ作用があります。発症から3日以内に投与するとウイルス量を大きく減らし、発熱や咳などの症状を早く改善する効果が確認されています。服用は1日1回、3日間で完結し、外来治療でも使いやすいのが特徴です。主な副作用は頭痛、下痢、肝機能異常などで、多くは軽度です。日本では2022年に緊急承認され、2023年に正式承認を受け、国産初のコロナ経口薬として広く使用されています。
デキサメタゾン(商品名は複数存在)
デキサメタゾンは、新型コロナウイルス感染症の重症化した患者に使用されるステロイド系抗炎症薬です。コロナの重症例では、ウイルスそのものよりも体の過剰な免疫反応(サイトカインストーム)が肺炎や多臓器障害を引き起こします。デキサメタゾンはこの炎症反応を抑え、免疫の暴走を防ぐことで呼吸状態の改善や死亡率の低下に寄与します。臨床試験(RECOVERY試験)では、酸素投与や人工呼吸が必要な患者で死亡率を有意に下げることが示され、世界的に標準治療薬として採用されています。一方、軽症患者では免疫抑制によって回復を遅らせる可能性があるため使用しません。投与は主に点滴または内服で行われ、副作用として高血糖、感染症リスク増加、消化性潰瘍などに注意が必要です。一般名で使用されることが多いです。
トシリズマブ(商品名:アクテムラ )
アクテムラ(一般名:トシリズマブ)は、もともと関節リウマチなど自己免疫疾患の治療に用いられる抗IL-6受容体抗体薬で、新型コロナウイルス感染症の重症化予防にも使用されます。COVID-19の重症例では、ウイルス感染によって免疫が過剰に反応し、炎症性サイトカイン「IL-6」が増加することで肺炎や多臓器障害が進行します。アクテムラはこのIL-6の作用を抑えることで、過剰な炎症反応を制御し、呼吸状態の悪化や死亡リスクの低下に寄与します。使用対象は酸素投与が必要な中等症〜重症の入院患者で、ステロイドと併用されることが多いです。投与は静脈注射で行い、体重に応じて量が決まります。副作用として感染症リスクの増加、肝機能障害、血液異常などがあり、投与中は慎重な観察が必要です。
バリシチニブ(商品名:オルミエント )
バリシチニブ(商品名:オルミエント)は、JAK阻害薬に分類される抗炎症薬で、新型コロナウイルス感染症の重症化予防に使用されます。COVID-19の重症例では、ウイルス感染による過剰な免疫反応(サイトカインストーム)が肺炎や多臓器障害を引き起こします。バリシチニブは、免疫細胞内のシグナル伝達経路であるJAK-STAT経路を阻害することで、炎症性サイトカインの作用を抑え、過剰な免疫反応を制御します。使用対象は酸素投与が必要な中等症〜重症の入院患者で、レムデシビルなどの抗ウイルス薬と併用されることが多いです。投与は主に経口または点滴で行われ、治療期間は数日間です。副作用として感染症リスクの増加、血栓症、肝機能障害、血球減少などがあり、使用中は血液検査や臨床状態の観察が重要です。
カシリビマブ・イムデビマブ(商品名:ロナプリーブ )
カシリビマブ・イムデビマブは、COVID-19の治療・予防に用いられる抗体カクテル療法です。二種類のモノクローナル抗体を組み合わせ、ウイルスのスパイクタンパク質に結合して細胞への侵入を阻止します。そのため、主に軽症から中等症の外来患者で重症化リスクが高い人に使用されます。また、感染後すぐの早期投与でウイルス量の減少や症状悪化の予防効果が報告されています。投与は点滴または皮下注射で行われ、単回投与で効果が期待できます。副作用は注射部位反応、発熱、アレルギー症状などがあり、使用中は医療機関での観察が必要です。ただし、新たな変異株によっては効果が低下する場合があり、使用可能性は流行株の状況に依存します。米国や日本では特定条件下での緊急使用が認められています。初期の変異株に有効でしたが、現在は一部の地域で使用制限あります。
ソトロビマブ(商品名:ゼブディ)
ソトロビマブ(商品名:ゼルルコビマブ)は、COVID-19の重症化リスクが高い外来患者向けの単回投与モノクローナル抗体薬です。新型コロナウイルスのスパイクタンパク質に結合し、ウイルスがヒトの細胞に侵入するのを阻止することで感染初期の増殖を抑え、入院や死亡のリスクを低減します。主に高齢者や基礎疾患を持つ軽症~中等症の患者に適応されます。投与は点滴または皮下注射で行われ、単回で効果が期待できるのが特徴です。副作用として注射部位反応、発熱、悪心、頭痛などが報告されており、使用中は医療機関での観察が推奨されます。ただし、新たなウイルス変異株によっては効果が低下する場合があり、適応状況は流行株に応じて判断されます。一部の変異株に有効とされています。
チキサゲビマブ・シルガビマブ(商品名:エバシェルド )
チキサゲビマブ・シルガビマブは、COVID-19の予防(特に重症化リスクの高い人向け)に用いられるモノクローナル抗体カクテル療法です。二種類の抗体を組み合わせることで、ウイルスのスパイクタンパク質に結合し、細胞への侵入を阻止します。そのため、ワクチン接種が困難な免疫抑制患者や高齢者など、感染リスクが高く重症化の恐れがある人に用いられます。投与は点滴または皮下注射で行われ、単回投与で数か月間の予防効果が期待されます。副作用として注射部位反応、発熱、頭痛、アレルギー症状などが報告されています。ただし、新型コロナウイルスの変異株によって中和活性が低下する可能性があるため、使用状況は流行株に応じて調整されます。米国や日本では、条件付きで緊急使用・予防薬として承認されています。
予防的にも使用される中和抗体療法です。
血漿療法
特定の商品名はなく、ドナー血漿が使用されます。
抗凝固薬
商品名として「エリキュース」「ザレルト」などがありますが、COVID-19治療においては一般名で用いられる場合が多いです。
これまで新型コロナウイルス治療は公費負担となっており、治療費の患者負担は0円でした。しかし2024年3月31日で当該公費負担は終了し、現在は健康保険の負担割合によって自己負担が生じます。薬によって自己負担額は異なりますが、1回の治療で2万円前後のものが多いです。なのでコロナ治療薬の処方希望の場合、処方する医師に自己負担額はどれくらいかかる確認すべきでしょう。また地域や国によって利用可能な薬剤が異なる場合がありますので、最新情報は医療機関や公的機関に確認してくだい。
監修 医師:今野正裕
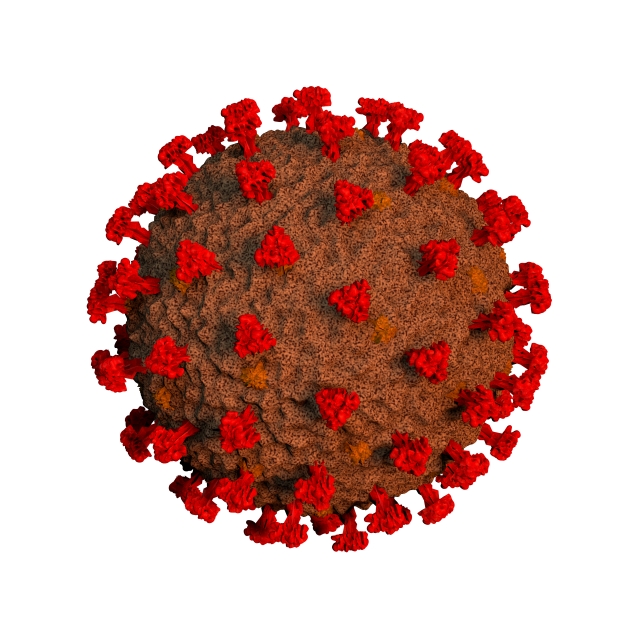
監修 医師:今野正裕
新宿、西新宿の内科、発熱外来、脳神経内科、整形外科は西新宿今野クリニックへ。予約はこちら。