メニュー
整形外科はこちら
脳神経内科はこちら
内科はこちら
健康診断はこちら
ワクチンはこちら
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00~ 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ●※ |
| 午後 15:00~ 18:00 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 |
初診の方とリハビリの方は、診療終了30分前までの受付となります。
【休診日】日祝、水曜午後、土曜午後 ※第2第4土曜
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00~ 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ●※ |
| 午後 15:00~ 18:00 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 |
初診の方とリハビリの方は、診療終了30分前までの受付となります。
【休診日】日祝、水曜午後、土曜午後 ※第2第4土曜
24時間365日ご相談を受け付けております!

ステロイドとは、ホルモンの一種で、体内で重要な役割を果たす化学物質です。医薬品として使用される「ステロイド」は、人工的に作られたもので、炎症を抑える効果などを持ち、いくつかの病気や症状の治療に用いられています。
コルチコステロイド(副腎皮質ステロイド)
ステロイドは、副腎皮質で生成されるホルモンを人工的に合成した薬で、強力な抗炎症作用と免疫抑制作用を持つことが特徴です。医療現場では、炎症性疾患や自己免疫疾患、アレルギー症状、喘息、関節炎、皮膚疾患など、幅広い疾患の治療に用いられています。ステロイドの働きは大きく分けて「抗炎症作用」「免疫抑制作用」「代謝・水・電解質調節作用」に整理できます。
まず、抗炎症作用についてです。炎症が起きると、免疫細胞からサイトカインやプロスタグランジン、ヒスタミンなどの炎症性物質が放出され、腫れ、発赤、痛み、発熱などの症状を引き起こします。ステロイドは細胞内受容体に結合し、これらの炎症性物質の産生を抑制します。これにより、血管の透過性の低下や白血球の活性化抑制が起こり、炎症による組織損傷や腫れを軽減します。そのため、関節炎や皮膚炎、喘息発作時の気道炎症などで即効性のある症状改善が期待できます。
次に、免疫抑制作用です。自己免疫疾患では、免疫系が自分の組織を攻撃するため炎症が持続します。ステロイドはT細胞やB細胞の働きを抑制し、抗体産生や免疫反応を低下させます。これにより、自己免疫疾患の活動性を抑え、症状の悪化や臓器障害を防ぐ効果があります。移植患者では拒絶反応の予防にも用いられます。
さらに、ステロイドには代謝や水・電解質の調節作用もあります。糖代謝を促進し血糖値を上昇させる作用があるほか、ナトリウムの再吸収を増やして体内の水分保持を促す働きもあります。これらの作用は、長期投与や高用量投与時に副作用として高血糖、浮腫、血圧上昇などを引き起こす原因となります。骨代謝にも影響を与え、骨粗鬆症や筋力低下のリスクもあります。
ステロイドは、その強力な抗炎症作用と免疫抑制作用を生かして、幅広い疾患の治療に使用されます。主に炎症性疾患、アレルギー疾患、自己免疫疾患、呼吸器疾患、皮膚疾患、血液疾患などで用いられます。
まず、炎症性疾患では、関節リウマチや全身性エリテマトーデス、多発性筋炎・皮膚筋炎など、自己免疫反応によって関節や筋肉、皮膚が炎症を起こす疾患に対して使用されます。炎症を抑えることで、痛みや腫れを軽減し、臓器障害の進行を防ぐことができます。
アレルギー疾患では、重症アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、アナフィラキシー、花粉症などで短期間の症状緩和に使われます。また、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患では、吸入ステロイドや内服・点滴で気道の炎症を抑え、発作の予防や症状の改善に役立ちます。
皮膚疾患でも、ステロイド外用薬は湿疹や接触性皮膚炎、乾癬などで局所の炎症やかゆみを抑えるために広く用いられます。炎症の強い部位には内服や注射での治療が行われることもあります。
さらに、血液疾患や免疫異常でもステロイドは有効です。自己免疫性溶血性貧血や免疫性血小板減少症など、免疫系が血球を攻撃する疾患で、免疫反応を抑制し血液成分の減少を防ぎます。臓器移植後には、拒絶反応の予防として免疫抑制目的で使用されることもあります。
その他、脳浮腫や腫瘍による炎症性症状、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)などでもステロイドが使われることがあります。短期間で炎症や免疫反応を強力に抑制できる一方、長期使用では副作用リスクがあるため、疾患の重症度や経過に応じて用量・投与期間を調整しながら使用されます。総じて、ステロイドは炎症や免疫異常が関与する多様な疾患に対して、症状緩和や病態進行の抑制を目的として幅広く使用される薬剤です。
ステロイドには、作用の強さや持続時間、投与方法によってさまざまな種類があり、疾患や症状に応じて使い分けられます。一般に使用されるステロイドは、内服薬、点滴薬、吸入薬、外用薬(軟膏・クリーム)、注射薬(関節内・筋肉内・皮下注射)の形態があります。
内服ステロイドはプレドニゾロン、メチルプレドニゾロン、デキサメタゾンなどが代表で、全身性の炎症性疾患や自己免疫疾患、急性増悪時の呼吸器疾患に用いられます。服用量は疾患の重症度や体重、治療目的に応じて調整され、急性期には高用量で短期間使用することもありますが、長期使用では副作用を避けるため漸減投与が必要です。
点滴ステロイドは、重症疾患や急性増悪時に即効性を求める場合に使用されます。静脈内投与により短時間で血中濃度を上昇させ、炎症や免疫反応を迅速に抑えることができます。急性喘息発作、重症関節炎、脳浮腫などで使用されることが多いです。
吸入ステロイドは主に喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)の長期管理に用いられ、気道に局所的に作用させるため全身への副作用を最小限に抑えられます。フルチカゾンやブデソニドなどが一般的です。
外用ステロイドは、皮膚炎、湿疹、乾癬などの局所炎症に使用され、症状の強さに応じて強度(弱〜強)を選択します。軟膏やクリーム、ローションの形態で、炎症部位に直接塗布することで局所的に作用し、副作用リスクが比較的低く抑えられます。
注射ステロイドは関節炎や腱鞘炎など局所の炎症に対して関節内注射や筋肉内注射で投与されます。局所に高濃度の薬を届けることで、痛みや腫れを迅速に改善しますが、頻回使用は軟骨障害や感染リスクを伴うため注意が必要です。
ステロイドは作用の即効性や全身・局所効果の違いに応じて使い分けられ、疾患の種類や重症度、患者の体質に応じた投与方法の選択が重要です。また、長期使用では副作用の管理や漸減が必要であり、安全に効果を得るために医師の指導の下で使用されます。
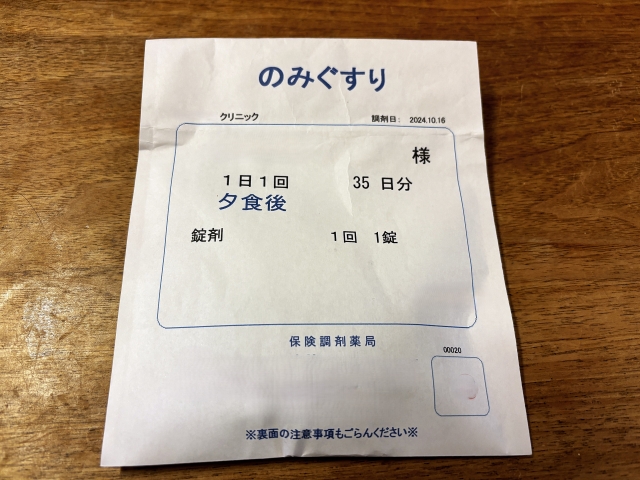
ステロイドは強力な抗炎症作用や免疫抑制作用を持つため、多くの疾患で有効に使用されますが、全身的な影響が大きく、副作用のリスクも高い薬剤です。副作用は使用量、投与期間、投与方法によって異なります。短期使用では比較的軽度ですが、長期使用や高用量使用では重篤な症状を引き起こすことがあります。
まず、代謝・内分泌系への影響として、血糖値上昇が挙げられます。ステロイドは肝臓での糖新生を促進し、インスリン抵抗性を高めるため、糖尿病の悪化や新規発症のリスクがあります。また、長期内服では副腎皮質の機能抑制が起こり、突然中止すると副腎不全を引き起こす危険があります。副腎不全では疲労感、倦怠感、低血圧、食欲不振などが現れ、場合によっては命に関わることもあります。
次に、骨・筋肉系への影響です。長期使用では骨吸収が促進され、骨粗鬆症や骨折リスクが高まります。また、筋タンパク分解が進むため、筋力低下や筋萎縮も起こりやすくなります。これにより、高齢者では転倒や日常生活動作の制限が増加する可能性があります。
心血管系・水・電解質の変化も副作用として重要です。ステロイドはナトリウムの再吸収を促進し、体液量を増やすため浮腫や高血圧を引き起こすことがあります。長期的には心不全や血栓症のリスクも増加します。また、カリウム低下による筋肉のけいれんや不整脈のリスクもあります。
さらに、消化器系の副作用として胃潰瘍や胃炎、消化管出血が起こることがあります。特にNSAIDsと併用した場合はリスクが高まります。免疫抑制作用により感染症のリスクも増加し、細菌感染やウイルス感染、真菌感染が重症化しやすくなります。
精神・神経系への影響も無視できません。ステロイド投与により不眠、気分の浮き沈み、抑うつ、易怒性が出ることがあり、長期高用量では精神症状の悪化や幻覚、妄想が現れる場合もあります。
皮膚・粘膜への影響もあり、皮膚の薄化、易出血性、創傷治癒遅延、にきびや毛深化などが報告されています。眼への影響としては、白内障や緑内障のリスクが増加することも知られています。
ステロイドの副作用は全身多臓器にわたり、多岐にわたるため、長期使用や高用量使用時には定期的な血液検査、骨密度検査、血圧・体重管理、糖尿病や感染症の監視が不可欠です。副作用のリスクを最小限にするためには、必要最小限の用量・期間での投与、漸減投与、局所投与や吸入投与の活用などが重要です。また、副作用が現れた場合には早期に対応することで、健康被害を抑えることが可能です。ステロイドは適切に管理すれば非常に有効な薬ですが、その利点とリスクを十分に理解し、医師の指導の下で使用することが不可欠です。
監修 医師:今野正裕
新宿、西新宿の内科、発熱外来、脳神経内科、整形外科は西新宿今野クリニックへ。予約はこちら。